|

[ 単行本 ]
|
イギリス国民教育に関わる国家関与の構造
・松井 一麿
【東北大学出版会】
発売日: 2008-07
参考価格: 3,675 円(税込)
販売価格: 3,675 円(税込)
Amazonポイント: 36 pt
( 在庫あり。 )
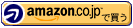

|
・松井 一麿
|
カスタマー平均評価: 0
|
|
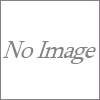
[ 単行本 ]
|
ハーバード大学の戦略
・デレック・C. ボック
【玉川大学出版部】
発売日: 1989-01
参考価格: 3,675 円(税込)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 3,669円〜
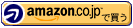
|
・デレック・C. ボック
|
カスタマー平均評価: 0
|
|

[ 単行本 ]
|
多言語社会の言語文化教育―英語を第二言語とする子どもへのアメリカ人教師たちの取り組み
・バトラー後藤 裕子
【くろしお出版】
発売日: 2003-05
参考価格: 3,990 円(税込)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 3,622円〜
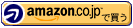
|
・バトラー後藤 裕子
|
カスタマー平均評価: 0
|
|
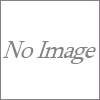
[ 単行本 ]
|
日本人教師の見た英国の小学校
・赤羽 昭夫
【日本図書刊行会】
発売日: 1996-10
参考価格: 1,223 円(税込)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 3,614円〜
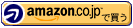
|
・赤羽 昭夫
|
カスタマー平均評価: 0
|
|

[ 単行本 ]
|
プロフェッショナルスクール―アメリカの専門職養成
・山田 礼子
【玉川大学出版部】
発売日: 1998-12
参考価格: 4,200 円(税込)
販売価格: 4,200 円(税込)
Amazonポイント: 42 pt
( 在庫あり。 )
中古価格: 3,580円〜
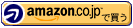

|
・山田 礼子
|
カスタマー平均評価: 0
|
|

[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
留学のススメ―そこんとこグアム
・倉内 J大志
【新風舎】
発売日: 1999-12
参考価格: 1,470 円(税込)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 3,580円〜
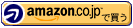
|
・倉内 J大志
|
カスタマー平均評価: 0
|
|
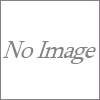
[ 単行本 ]
|
サバンナの風に吹かれて―タンザニア・ムエカ大学留学記
・富永 純平
【近代文芸社】
発売日: 1996-02
参考価格: 2,039 円(税込)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 3,560円〜
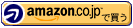
|
・富永 純平
|
カスタマー平均評価: 0
|
|

[ 単行本 ]
|
戦後台湾教育とナショナル・アイデンティティ
・山崎 直也
【東信堂】
発売日: 2009-03
参考価格: 4,200 円(税込)
販売価格: 4,200 円(税込)
Amazonポイント: 42 pt
( 在庫あり。 )
中古価格: 3,549円〜
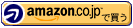

|
・山崎 直也
|
カスタマー平均評価: 0
|
|

[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
諸外国の教育改革―世界の教育潮流を読む 主要6か国の最新動向
・本間 政雄 ・高橋 誠
【ぎょうせい】
発売日: 2000-07
参考価格: 3,800 円(税込)
販売価格: 品切れ中
中古価格: 3,489円〜
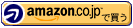
|
・本間 政雄
・高橋 誠
|
カスタマー平均評価:  5 5
 とても参考になります。 とても参考になります。
1980年頃からの教育改革の動向が提示されています。
特に,それぞれの年代の関連性が的確に述べられているので、
読みやすく,理解しやすいと思います。
教育改革の背景と経緯,改革の方向性が
初・中・高等教育,教員養成の側面から書かれています。
また、各国の学校系統図も載せられているので、
初心者用としても最適です。
|
|

[ 単行本 ]
|
ラオス少数民族の教育問題
・乾 美紀
【明石書店】
発売日: 2004-02-19
参考価格: 4,200 円(税込)
販売価格: 4,200 円(税込)
Amazonポイント: 42 pt
( 在庫あり。 )
中古価格: 3,487円〜
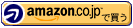

|
・乾 美紀
|
カスタマー平均評価:  3 3
 素晴らしい研究成果ですが、データの取り方、分析が雑 素晴らしい研究成果ですが、データの取り方、分析が雑
モンとラオが混在するシェンクワンの村に入り、実際に参与観察をすることができ、しかも英語教師として
教える場を与えられるという、あの調査の難しいラオスでどうやってそんな参与観察ができたの?という研究です。おそらく、ラオスの教育問題に対する筆者の研究成果は正しいものであろうと思いますし、文章は簡便で
読み進めやすく、参与観察についてもある程度詳しく書かれていて事情も読み取りやすい、おもしろいものになっています。 少数民族の教育問題についてのフィールド研究は数が少なく、調査の仕方など非常に参考になりましたが、
一方で2,3ヶ月という短期間で教育問題を探ることの限界も感じました。例えば、「ラオはモンよりも良い立場にあると思うか」
という誘導的なアンケートの結果で75%のラオがyesと答えたことでエスノセントリズムと結びつけるのは早計でしょうし、
例えばラオのほうが豊かだから、という回答も客観的に考えた結果かもしれません。
また、モンの子にラオ語よりも英語を学びたいという傾向が強い、とありますが根拠として家のテレビなどからすでに
タイ語やラオ語を学んでいる例外的な子のインタビューを用いており、やはり雑です。保護者のインタビューの中に
外部の出身のおばあさんが含まれているなど、??なデータの取り方も
多く、もしかしたら本の中に書かれていない
深い理由があるのかもしれませんがわかりません。ある程度引いて読んで素晴らしい
研究だと思うものの、もっともっと、より細かく調査していってほしいと思います。
 博士論文としてきっちり押さえどころがしっかりしている 博士論文としてきっちり押さえどころがしっかりしている
ラオスの少数民族の教育問題というニッチな研究の博士論文である。現地に入らなければ入手できない豊富なデーターを駆使して、論理的に議論を進めています。他に類を見ない貴重な書であることは確かです。 惜しむらくは滞在期間が短かったせいか、研究の視点が表面的に感じられた。ラオスの少数民族の教育問題は教育が問題なのではなく、少数民族政策に根源があり、その政策のバックボーンとなるラオス政府および多数派の低地ラオ族の意識および歴史についての考察を教育および文明史の観点から掘り下げて行かなければ読者は消化不良の感じを得てしまいます。
|
|



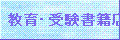
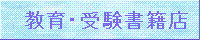











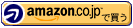

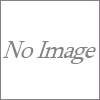





 5
5
 3
3